清水寛「続・生きること学ぶこと」沖縄タイムス02.4.27
やしまたろう作『道草いっぱい』「待合室文庫」『小児歯科診療』2002年10月より
川島浩『シャッターを切る心』書評『赤旗』2002年11月30日より
清水寛『続・生きること学ぶこと』『障害児教育の過去と現在』2002年12月6日 日本教育新聞より
木島始『ぼくらのペガサス』『飛ぶ声をおぼえる』評「交野が原」52号

本書は、編著者の清水寛・埼玉大学教育学部教授(今年三月定年で退職)が「障害児教育概論」の授業で取り入れたゲストたちの講話集である。二十二人のゲストは、自身や家族がハンディキャップ(障碍)に直面し、苦難と向き合って生きてきた人たち。
ハンセン病回復者、重度脳性まひ、視覚障害者、超重度障碍児や自閉症児の親、入院児童の訪問教育、盲・ろう、心身障碍学級などでの表現活動教育、韓国で植民地時代の「日の丸抹消事件」をテーマに授業した日本人教師、三十七年間かかわった夜間中学教師、非行少年とかかわる救護院職員、在日韓国人二世らの肉声を二段組五百五十ページに収めた大冊だ。
目を通すと、本の厚さを感じさせないほどに読み進んでいく。ゲストのリアルな生活体験と、生まれでた「命」の尊さを実感させる人間愛にあふれた内容にひきつけられていく。事故で後天的に脳障害を受けた息子を在宅で世話する母親は「なにもしゃべれない状態ですが、海くんの生命と向き合って暮らせる喜びというか、…無駄な価値のない生命というのはないんじゃないかと思う」と述べる。この記述には、論議のある生命と尊厳について考えさせられる。
沖縄とのかかわりではハンセン病回復者、視覚障害、教育のため本土に移った自閉症児の親らが登場。平和教育の場として存在などが取り上げられ、沖縄の社会状況にも関心が向けられている。講話後の学生と講師のキャッチボール(感想文)も本書を深め、興味深いものにしている。
小児がんで十一歳の息子を亡くした母親はつづっている。「浩一よ、苦しみも代わってやれず励ますのみの無力なママを許してください。…天国でもみんなから愛されますように。またいつしか会える日までさようなら。」早世した、いとし子と肉親らの再会と語らいのために「あの世」はあってほしい。この本を手にして私の小さな世界観は変わった。
(沖縄タイムス記者・謝花勝一)
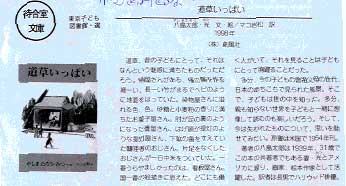
道草、昔の子どもにとって、それはなんという魅惑に満ちたものだっただろう。桶屋さんがある、桶の輪を作る細一い、長一い竹がまるでヘビのように地面をはっていた。染物屋さんに溢れる色、色。砂糖と小麦粉の香りに満ちたお菓子屋さん。肘が足の裏のようになった畳屋さん、はげ頭が提灯のような提灯屋さん、下駄の歯をすえていた聾唖者のおじさん。片足をなくしたおじさんが一日中米をついていた。一番うらやましかったのは、看板屋さん。国一番の絵描きに思えた。どこにも働く人がいて、それを見ることは子どもにとって胸躍ることだった。
多分、今の子どもの曾祖父母の世代、日本のあちこちで見られた風景。そこで、子どもは世の中を知った。多分、親も知らない世界を子どもと一緒に想像して読むのも楽しいだろう。そして、今は失われたものについて、思いを馳せてみたい。原書は米国で1954年刊。
著者の八島太郎は1939年、31歳でこの本の共著者でもある妻・光とアメリカに渡り、画家、絵本作家として活躍した。訳者は長男でハリウッド俳優。
「待合室文庫」『小児歯科診療』2002年10月より
書評『シャッターを切る心』

一九五二年の警官隊による民衆の弾圧「メーデー事件」の写真で、脚光を浴びた写真家・川島浩さん。その後、ラオス解放区を取材した「洞窟を出た人びと」、京都・与謝の海養護学校など人間をテーマに撮り続けてきました。近刊の写真集『シャッターを切る心』(創風社)は、九一年から四年間、雑誌「女性のひろば』で連載した作品をまとめたもの。川島さんの問題意識が伝わってきます.
写真家
川島浩さん
働く、学ぶ、遊ぶ表情を全国に追う
イカ漁の町、加賀友禅の技…
こだわって「一瞬を待つ」
☆全都道府県回り,「編集部から好きなように撮っていいといわれたんでね。楽しい仕事でした本当は『ふるさとのうた』なんてタイトルだと、とっつきやすいんだろうけど、今回は『こんな気持ちで写真を撮ってるんだ』ということを文章に書いたから。読者をごまかさない、うそいつわりのないタイトルです」
全都道府県を回り、その土地ならではの情景を切りとりました、そして登場する人物は、窯場で仕事に集中する女性や好奇心いっぱいの保育園児など、どれも印象的な表情を見せます。
石川県の加賀友禅の作業場で一心に布に糊(のり)伏せしている女性を撮った「色をさす」。張り詰めた表情と描き出される絵柄を一枚に収めました。
イカ漁の最盛期迎えていた佐賀の東松浦半島では、港町を撮影した後も日暮れまで被写体を探し歩きます。「イカ漁の取材で港町だとあたりまえの風景でしょ。それで夕日をバックに生干しイカのカーテン写していたとき、小さな女の子がイカの取りこみを手伝い始めた。あまりにもほほえましくて、思わず撮りました」
ぎりぎりの明るさで撮ったノーフラッシュの写真は、その場で感じた夕暮れ時の雰囲気を大切にしたいとの思いからです。
取材期間は一作品につき平均一週間。農作業や行事などの流れをつかみ、シャッターチャンスを待ちます。岡山では目的の五重塔が工事中で青いカバーが掛けられていたハプニングもありました。急きょ倉敷に変更し、一年後、独自に岡山の五重塔を取材し本書に収録。「だって、悔しいじゃない」と笑います。
★与謝の海養護学校
仕事の根底にあるのは「いいかげんなものや納得できないものは撮らないしという姿勢。写貞集『ほくらはみんな生きている』(七九年)の京都・与謝の海養護学校の取材の話からもうかがえます。社会への告発でなく、ありのままの子どもたちを写してほしいと願う学校側からの依頼。しかし、二度断ったといいます。
「依頼の前に、何かの展覧会で数点の障害児の写真を見たんです。両手が動かない子がマカロニかなんかを食べていた。なぜこの場面なのか。見せ物のような写真だと感じました。そのとき自分には撮れないと思って」
ついに折れて取材にいったときも何も撮らず、子どもたちの日常を見させてもらうだけにしました。初めてシャッターを押したのは二度目の訪問でした。
「それまでにもハッとする場面は何度もありました。でも、それがただめずらしいだけなのかどうか判断するのには時間が必要。初めて撮ったのは、小児まひの後遺症で言葉がスムーズに話せなくて、もどかしそうだったあの子じゃないかな」
動かない体で精いっぱい自分の気持ちを周りに説明している子ども。生きようとしている姿、泡える苦悩、自分のなかでのたたかいが入りまじったこの表情を残したいと思ったと当時を語ります。
写真を単なる記録でなく表現として認識した二十代から「リアリズム」にこだわり続けています。大学卒業後に勤務した日本水産の塩釜出張所で同僚にすすめられ写真を始めました。同時に「リアリズム」に関する文学、美術、写真等の文献を熱心に読みました。そして「たんなる写実でなく、物事の本質を写すこと」にたどりつきました。「事件や社会問題でも、あぶくみたいに出てくるうわべだけの現象を撮ってもリアリズムじゃない。社会の成り立ちや進むべき方向、どんな人たちが担っていくのか知ったうえで何が本質か見極めることが大事です」
例えば人物。まず観察し、どんな考えを持っているのか、本心で話している言葉なのかじっくりみます。
☆失敗を重ねて・
しかし、実際はシャッターを押せば写る写真に、若いころは何度も失敗を重ねたと振り返ります。
「写真家として駆けだしのころ、よく座談会の写真の依頼を受けました。ピントがあっていれば安心はするけど、外形だけのものになってしまう。作家や芸術家ならその作品がにじみ出てくるような表情を撮らなきゃ」
自分でも満足のいく顔を撮るのに十年かかったといいます。「それも流され続けた十年じゃなくて、本当の仕事の質を求め続けた十年でなけりゃあね」
できるだけ多くの視点からとたった二本のフィルムを仲間と分げへ合った「メーデー事件」、「見せ物」を拒絶して写した障害児の生きる姿。一瞬を追いつづける写真家の執念が、物事のへ本質を刻み、次代に伝えます。
文・中村尚代記者
写真・林 行博記者
かわしまひろし=一九二五年東京生まれ。写真家・田村茂氏に師事。日本リアリズム写真集団(JRP)理事長。日本写真家協会会友、主な写真集に「未来誕生』『あすを拓く子ら』『ヒトが人間になる』ほか。
障害児教育の過去と現在
戦火が激しくなった昭和十九年当時、東京市立光明学校(現東京都立光明養護学校)に寄宿していた生徒と教職員は、校庭の隅に大きな防空壕を掘り「現地疎開」していた。普通学校と違い、同校には疎開先が割り当てられなかったためだ。その後、松本保平校長が奔走し、佐藤彪也教諭など当時の教職員が医療器具を抱え長野に疎開した。校舎のほとんどが空襲で焼けたのは、その十日後だった。
本書にはこうした障害児教育について、戦時下の学校の姿や、現在の学校・学級での実践、親の取り組み、海外の教育現場など、当事者によるさまざまな講話が収められている。全国障害者問題研究会の委員長を務めていた編著者が、埼玉大学教育学部の「障害児教育学概論」で行ったゲスト講話二十三編を一冊にまとめた。
本書には障害児教育だけでなく、児童自立支援施設や夜間中学の教職員、在日韓国
人二世、ハンセン病回復者ら、さまざまな立場からの貴重な講話も収録している。教員を目指す学生に、広い視野を持ってほしいと願って企画された授業だったことが分かる。
障害児教育の過去から現在を縦糸とすれば、それ以外の講話を横糸に編むことで、現在の教育や社会の一つの姿が浮かんでくる。
「障害児教育は教育の原点」という言葉が、改めて思い出される。(通)
2002年12月6日 日本教育新聞より
大人のための児童文学
木島始『ぼくらのペガサス』『飛ぶ声をおぼえる』評「交野が原」52号
満谷マーガレット
「子供だまし」という言葉があるように、子供はだましやすいと思っている大人が多いようだ。しかし、「裸の王様」の話しに見られるように、大人の方がずっと騙されやすいこともある。もっとも弱い立場にいるはずの子供が、王様の嘘やごまかしを見抜く話が大人にとって爽快なのは、権力者の言葉にふりまわされている大人たちが子供の物語でしか出会えない健全でラジカルな常識に飢えているからだろう――たとえそれが大人社会の現実には通用しないとわかっていても。
『ぼくらのペガサス』という物語に、そうしたラジカルな常識は生きている。原爆の光線で目がくらんで飛べなくなった天馬のために、カンイチ少年は動物仲間と力を台わせて、「ピカドン止メサセロ」と総理大臣に訴えかける。太陽を奪うことで大人たちから原爆を飛ばさない約束を引き出す、というのは奇想天外な結末だが、物語全体が現実離れしているわけではない。例えば、カンイチくんたちのメッセージを持ってきたヒヨドリのピッピーに昼寝を邪魔された総理大臣が「ネゴトヲイウンデナイ、ワシャイソガシインダ」とうそぶきながらまた寝てしまう場面は、「唯一の被爆国」の戦後政治における倦怠と無力を浮き彫りにしている。「ぼくらのべガサス」が書かれた一九六六年の時点で、天馬が再び飛べるようになったものの、カンイチくんたちはまだ安心できないでいた。彼らの活躍が今もって必要だとというのは悲しいことだ。
なお、この本には表題作以外に物語が四つ、詩が三篇、エッセイが二つ入っているが、著者自身があのキノコ雲を見るにいたった経緯を描くエッセイ「十五歳の分かれ道」を『ぼくらのペガサス』と読み合わせると興味深い。著者がこのエッセイの中で言及している、戦争に散った同級生を描いた小説『春の犠牲』が再販されることを、筆者は願う。
もう一つのエッセイは「迎え入れたお客さん」と題されているが、タイトルの「お客さん」はヒミコの時代に中国から渡ってきた漢字であり、そこから生まれた本である。大事な「お客さん」なのに売れ残ったものを裁断し、紙屑にしてしまう出版社は、やはり「健全な常識」をどこかに置き忘れてきたといっていい。このエッセイには本にささげた四行詩が四つ入っているが、一つだけ引用したい。
倒れるまでの ものすごい
旅のかずかず 話してくれる
本という本は 人待ち顔して
静まりかえった お客さんだ
さて、『飛ぶ声をおぼえる』ほ恐竜の詩で幕を開け、その末裔である小鳥で終わる。「恐竜のたましい」という詩には、子供たちの生の声が聞こえてくる。「いかついなあ! うおっきいなあ! /こわあい きみっるー いきてるの?」子供たちを惹きつけて止まないのは恐竜だが、その「たましい」を引き継いだ小鳥こそ「あっぱれ と称えたい生きもの」なのだ。彼らは私たちにいろんなことを教えてくれる。巻末の詩「小さな鳥へのほめうた」は残念ながら教科書には載りそうにないから、第二聯をここに引用しておく。
ひばりはいばりやか?
ノー… たらたらごじまん
いばりやなんか ひばりは
ちっぽけく たまげさせるさ
「マヨイノもりの五つのむかしばなし」には大変な「いばりや」が登場する。ヒフミ村で刀を持つことを許されたただ一人の侍ゴロベエがその人だが、彼はお箸を徳利につけこんで、その先をなめることで、お酒を「飲む」ほどのけちんぼでもある。ゴロベエは村外れのマヨイノ森のなかで迷いにまよって、子供のシロウとヤエとの知恵比べにも負かされてばかりいる。五つ目の話「レンギョさま」には、そんな利口な子供たちさえ捕まえられない「ふしぎないきもの」が登場するところが、またいい。ハスの花をおしひらくこの「ふしぎないきもの」を誰も見たことがないのに、ヒフミ村の住民は皆その存在を信じて疑わない。昭和三十年代を舞台にした「おばけを見に行く」という話では、大人たちのおそれるお化けの正体を子供たちがあっさりとつきとめてしまう。戦後の生活は明るくなったが、「不思議な生きもの」が潜む蔭の意味合いがめっきり減ったようだ。
不思議な物語をもう一つ紹介しよう。「ヒマラヤの笛」は二冊を通じて唯一の翻訳で、「あとがき」によると原作者のA・ラマチャンドランはインドの独創的な画家だ。この話は一度絵本として出版されたというが、絵はなくとも活字を追いながら、魔法の笛によって美しい花園に生まれ変わった貧しい畑の様子を想像され、それはそれで充分楽しい。
不思議な生き物といえば、誰でも思い浮かべるのは竜だろう。「かくれ竜のはなし」は、タツドシの著者が自分の干支を廻る回想から始まる。幼い頃、「タヅドシやから…」とその意味も判らないまま、ある性格を押しつけられた気持ちになって当惑した著者は、日本が軍国主義に染まる頃に中学生となった。号令に振り回されているうちにある日突然、ふざける同級生に暴力を揮った時、誰よりも自分が驚いたという。残忍で強暴な竜はすべての人間の内部に潜んでいて、状況しだいでそれがひょっこり顔を出す。「かくれ竜」の本当の恐ろしさは、ここにある。しかし、視野をアジア全体に広げると、さまざまな竜が見えてくる。踊り出すと「めでたい五色の雲」が浮かび上がる中国の竜。そして獄中のホー・チ・ミンが書いた字謎の漢詩(籠=竹の牢)に隠された竜。さて、これからどちらの竜が動き出すのだろうか。
この二冊には、本島始の遊び心がいっぱいつまっている。それは、しかしキマジメなどこまでも詩人の遊びだ。機智とユーモアをしっかり解する読者にめぐりあい、騙されやすい大人が一人でも減れば、と心から願う次第である。